医療慣行で十分とは限らない
クスリの副作用とは怖いもので私も交通事故後に処方されたクスリで重大な副作用に見舞われたことがある。幸い転院後の主治医に初診で服薬の中止を指示され、薬を飲むのを止めてから熱も下がり薬疹も消えた。初診時に行った血液検査では、主治医に覚醒剤を疑われるほど肝臓が危ない状態だった。より詳細な血液検査でB型肝炎でもC型肝炎でもないことが分かり、薬の副作用という結論になった。その後の血液検査では肝臓の状態が元に戻っていて、服薬の中止が正解だったことがはっきりした。日記を読むと当時の様子が書いてあって、他人事のように「死んでいたら裁判になっただろうなぁ」と思った。
薬の副作用に関しては重要な判例がある。副作用を責める裁判ではなくて副作用に対する医師の注意義務について裁判であり、手術中の麻酔剤による副作用であるが…。
人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであるが(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、具体的な個々の案件において、債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(最高裁昭和五四年(オ)第一三八六号同五七年三月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事一三五号五六三頁、最高裁昭和五七年(オ)第一一二七号同六三年一月一九日第三小法廷判決・裁判集民事一五三号一七頁参照)。そして、この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものであるが(最高裁平成四年(オ)第二〇〇号同七年六月九日第二小法廷判決・民集四九巻六号一四九九頁参照)、医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。
ところで、本件麻酔剤の能書には、「副作用とその対策」の項に血圧対策として、麻酔剤注入前に一回、注入後は一〇ないし一五分まで二分間隔に血圧を測定すべきであると記載されているところ、原判決は、能書の右記載にもかかわらず、昭和四九年ころは、血圧については少なくとも五分間隔で測るというのが一般開業医の常識であったとして、当時の医療水準を基準にする限り、被上告人aに過失があったということはできない、という。しかしながら、医薬品の添付文書(能書)の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)につき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者が、投与を受ける患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で記載するものであるから、医師が医薬品を使用するに当たって右文章に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されるものというべきである。そして、前示の事実に照らせば、本件麻酔剤を投与された患者は、ときにその副作用により急激な血圧低下を来し、心停止にまで至る腰麻ショックを起こすことがあり、このようなショックを防ぐために、麻酔剤注入後の頻回の血圧測定が必要となり、その趣旨で本件麻酔剤の能書には、昭和四七年から前記の記載がされていたということができ(鑑定人nによると、本件麻酔剤を投与し、体位変換後の午後四時三五分の血圧が一二四ないし七〇、開腹時の同四〇分の血圧が一二二ないし七二であったものが、同四五分に最高血圧が五〇にまで低下することはあり得ることであり、ことに腰麻ショックというのはそのようにして起こることが多く、このような急激な血圧低下は、通常頻繁に、すなわち一ないし二分間隔で血圧を測定することにより発見し得るもので、このようなショックの発現は、「どの教科書にも頻回に血圧を測定し、心電図を観察し、脈拍数の変化に注意して発見すべしと書かれている」というのである)、他面、二分間隔での血圧測定の実施は、何ら高度の知識や技術が要求されるものではなく、血圧測定を行い得る通常の看護婦を配置してさえおけば足りるものであって、本件でもこれを行うことに格別の支障があったわけではないのであるから、被上告人aが能書に記載された注意事項に従わなかったことにつき合理的な理由があったとはいえない。すなわち、昭和四九年当時であっても、本件麻酔剤を使用する医師は、一般にその能書に記載された二分間隔での血圧測定を実施する注意義務があったというべきであり、仮に当時の一般開業医がこれに記載された注意事項を守らず、血圧の測定は五分間隔で行うのを常識とし、そのように実践していたとしても、それは平均的医師が現に行っていた当時の医療慣行であるというにすぎず、これに従った医療行為を行ったというだけでは、医療機関に要求される医療水準に基づいた注意義務を尽くしたものということはできない。
(事件番号「平成4(オ)251」平成8年01月23日 最高裁判所第三小法廷判決)
一部を強調表示させてもらった。
今日、『【対談】医療崩壊を防ぐために』という記事を読んだら、次のように書いてあった。
重大な過失,標準的な医療行為の定義とは
舛添 さらに,先ほどの「重大な過失」がある事例というのは何なのかということについて,「診療録などの改ざん,故意や重大な過失のある事例,その他悪質な事例であると認めた場合に限って,適時適切に通知を行う」となっているのですが,患者が死んだという結果が「重大な過失」ではない,ということです。では「重大な過失」とは何かというと,「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療行為を行った場合」というのだけれども……。
岡井 そこが問題なのです。その「標準的な医療行為から著しく逸脱した」というのが何であるのかが。
舛添 「標準的な医療行為から著しく逸脱した」とは何であるか,これは議論があるだろうとは思います。ただ,患者さんが亡くなったから重大な過失だということではないということを明言します。
(医学書院/週刊医学界新聞(第2785号 2008年06月16日)【対談】医療崩壊を防ぐために)
「標準的な医療行為」という言葉が出てきて、すぐに『事件番号「平成4(オ)251」最高裁判決』が浮かんだ。「標準的な医療行為」が最高裁判決文の「平均的医師が現に行っている医療慣行」だとしたら、「医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない」というのが司法の判断なので、「標準的な医療行為」では「医療水準に従った注意義務を尽くした」と言えない場合がありそうである。もしも医師が「平均的医師が現に行っている医療慣行」で十分だと考えているとしたら、甘いだろう。
実は、後に、『事件番号「平成4(オ)251」最高裁判決』よりも厳しい最高裁判決があった。
(1)精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する向精神薬の副作用については、常にこれを念頭において治療に当たるべきであり、向精神薬の副作用についての医療上の知見については、その最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるというべきである。本件薬剤を治療に用いる精神科医は、本件薬剤が本件添付文書に記載された本件症候群の副作用を有することや、本件症候群の症状、原因等を認識していなければならなかったものというべきである。そして、原審の認定によれば、前記2のとおり、本件症候群は皮膚粘膜の発しん等を伴う多形しん出性紅はん症候群の重症型であり、その結果として失明に至ることもあること、その発症の原因としてアレルギー性機序が働くものと考えられていたことが認められる。
また、本件記録によれば、昭和61年3月当時、これらの知見のほか、薬しんの大半がアレルギー性機序によって発生するものであることや、アレルギーの関与する種々の類型の薬しんが相互に移行し合うものであり、例えば、限局型で軽症型の固定薬しんが急激に進行して汎発型で重症型の本件症候群や中毒性表皮壊死症型に移行することのあることなどが一般の医師においても認識可能な医療上の知見であったことがうかがわれる。このことからすると、本件添付文書に記載された(1)及び(2)の症状は、相互に独立した無関係な症状とみるべきではなく、相互に移行可能な症状であって、(1)の症状から(2)の症状へ移行する可能性があったことがうかがえる。
なお、本件添付文書に記載の(1)の症状は、「過敏症状」として「ときに猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹などの過敏症状があらわれることがある」とするが、文意に照らせば、「猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹」などは直ちに投薬を中止すべき症状の例示にすぎず、副作用としての過敏症がそこに掲げられたものに限定される趣旨とは解されない。
(2)本件においては、3月20日に薬剤の副作用と疑われる発しん等の過敏症状が生じていることを認めたのであるから、テグレトールによる薬しんのみならず本件薬剤による副作用も疑い、その投薬の中止を検討すべき義務があった。すなわち、過敏症状の発生から直ちに本件症候群の発症や失明の結果まで予見することが可能であったということはできないとしても、当時の医学的知見において、過敏症状が本件添付文書の(2)に記載された本件症候群へ移行することが予想し得たものとすれば、本件医師らは、過敏症状の発生を認めたのであるから、十分な経過観察を行い、過敏症状又は皮膚症状の軽快が認められないときは、本件薬剤の投与を中止して経過を観察するなど、本件症候群の発生を予見、回避すべき義務を負っていたものといわなければならない。
(事件番号「平成12(受)1556」平成14年11月8日 最高裁判所二小法廷判決)
これも一部を強調表示させてもらった。
事件番号「平成12(受)1556」は精神科医の処方する向精神薬の副作用についての裁判で、事件番号「平成4(オ)251」のような他の診療科の薬にも当てはまるのかどうか分からない。とにかく、「最新の添付文書を確認」するのは事件番号「平成4(オ)251」により当然だとして、「必要に応じて文献を参照するなど、当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務がある」というのは、とても厳しい判決だと思った。しかし、医師にはそのくらいの努力が求められているのだろう。『人の生命及び健康を管理すべき業務』なのだから。それに、その苦労に見合った報酬が得られる(参照)のだから。
この事件番号「平成12(受)1556」についてはネット上に解説を見つけた。
・『薬剤の副作用を予見・回避すべき義務を負っているとみなされた事例』民間医局、医療過誤判例集 Vol.3
事件番号「平成4(オ)251」も事件番号「平成12(受)1556」も投薬時の注意義務であり、他の医療行為での注意義務でも同様の判決になるかどうかは分からない。でも、『平均的医師が現に行っている医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない』という判示は、他の医療行為に当てはめても良いと思う。




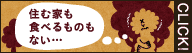








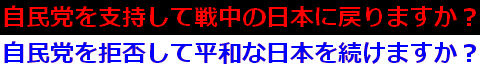

コメント 0